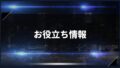リスティング広告を運用していると、玄人ならではの「あるある」に遭遇する瞬間があります。その中でも特に共感を呼ぶのが、「RLSAのオーディエンスリストが細かすぎて、管理画面で迷子になる」という状況。今回は、この現象について深掘りしつつ、なぜこうなるのか、どう対処すればいいのかを考えてみます。
RLSAって何?(おさらい)
RLSA(リマーケティングリスト・フォー・サーチ・アズ)は、Google広告の強力な機能の一つ。過去にサイトを訪れたユーザーを対象に、検索広告の入札やクリエイティブをカスタマイズできる仕組みです。例えば、「商品ページを見たけど買わなかった人」や「カートまで行ったけど離脱した人」といったセグメントを作って、それぞれに最適化を図るわけです。リスティング運用者の腕の見せ所ですよね。
細分化の誘惑に負ける瞬間
最初はシンプルに「全訪問者」「コンバージョン済みユーザー」くらいで始めます。でも、運用に慣れてくると欲が出てくる。「30日以内に商品Aのページを見た人」「過去90日でブログを3回以上読んだ人」「特定のカテゴリに興味があるけど購入に至ってない人」…と、どんどん細かくリストを分けちゃうんですよね。だって、それでCVRが上がるかもしれないし、CPAが下がるかもしれないって思うじゃないですか。
で、オーディエンスリストが10個、20個と増えていく。挙句の果てには「初回訪問から7日以内に特定LPを見て、モバイル端末で閲覧した人」みたいな超ニッチなリストまで作っちゃう。自分では「これで完璧!」って満足してるんですけどね。
そして迷子になる
ある日、管理画面を開いてキャンペーンを見直そうとしたとき、事件は起こります。オーディエンスリストのタブを開くと、そこには見慣れない名前のリストがズラリ。「『Cart_90d_noCV』って何だっけ?」「『Blog_3x_30d』は誰向けだっけ?」と、自分で作ったはずなのに記憶が曖昧。命名ルールも途中でブレてきて、「ProdA_view」と「ProductA_30d」が混在してたりして、もうカオス。
挙句の果てに、キャンペーンに紐づけたリストを見ても「これ、どのセグメント狙ってたんだっけ?」と自分自身にツッコミを入れる羽目に。玄人なら一度は経験するこの感覚、笑うしかないですよね。
なぜこうなるのか?
原因はシンプル。細分化しすぎると管理が追いつかなくなるんです。RLSAの強みはターゲティングの精度にあるけど、人間側の脳みそには限界がある。リストが増えるほど、それぞれの成果をトラッキングして最適化する手間も増えるし、そもそも「このリスト意味あったっけ?」って見直す時間すら取れなくなってくる。
さらに、クライアントやチームで共有するならまだしも、個人で運用してると命名規則や意図が自分の中だけで完結しちゃうから、後で振り返ると迷宮入りするんですよね。
対処法はあるのか?
この「迷子あるある」を回避するには、いくつかコツがあります:
- 命名ルールをガチガチに決める
例えば「[目的][期間][条件]」みたいに、「Cart_30d_noCV」(カート入り、30日、未購入)とか統一感を持たせる。後で見ても一目瞭然になります。 - リストの数を絞る
細かく作りすぎず、「これ本当に必要?」って自問自答しながら厳選。成果が出てないリストは潔く削除するのも大事。 - メモを残す癖をつける
管理画面にメモ機能があれば活用するし、なければエクセルやスプレッドシートに「このリストの意図」を記録しておく。未来の自分へのラブレターだと思って。 - 定期的に見直す
月1くらいでリストを棚卸しして、「使ってないやつ」「成果出てないやつ」を整理。迷子になる前に予防線を張るんです。
まとめ:玄人ならではの愛すべき葛藤
RLSAのオーディエンスリストが細かすぎて迷子になる瞬間って、リスティング運用者の「もっと良くしたい!」っていう情熱の裏返しなんですよね。最適化を追求するあまり、自分で自分の首を絞める。でも、その葛藤があるからこそ、上級者として成長できるんだと思います。
次に管理画面で「このリスト誰向けだっけ?」ってツッコミ入れたときは、ちょっと笑って、ちょっと見直して、また前に進みましょう。リスティング玄人なら、このあるあるを乗り越えられるはずです!

リスティング広告の運用・コンサルティング
フリーランスマーケター「デジマク」